トピックスTOPICS
東京オリンピックが与える影響 ~期間中、都内で働く人はどうなるの?~
東京オリンピック開催まであと半年を切りました。
最近、ニュースを見ていても、いろいろ盛り上がってきているなという印象を受けます。
今回は、そんな東京オリンピックが私たちに与える影響についてご紹介していきます。
東京オリンピック・パラリンピックに関して
開催期間
2020年7月24日(金)に開会式~8月9日(日)の閉会式まで
※サッカー、ソフトボールは7月22日(水)より開始
大会期間中の祝日移動
【海の日】7月第3月曜日 → 7月23日(木)のオリンピック開会式前日
【スポーツの日(体育の日)】10月第2月曜日 → 7月24日(金)のオリンピック開会式当日
【山の日】8月11日 → 8月10日(月)のオリンピック閉会式翌日
7月の第3週目は、例年の海の日の3連休だけではなく、平日が3日間となるため、実働日が減り、業務の圧縮が例年以上に予想されています。
交通機関の混雑
・バス、自動車(道路)
首都圏で高速道路と一般道で交通規制が実施されます。さまざまなシミュレーションも実施されていますが、渋滞の状況は路線によってかなり差があるようです。
※首都高は期間中、日中の料金を1000円値上げする予定です。
・鉄道(駅)
オリンピック準備局のサイトで「大会輸送影響度マップ」というものが公開されています。
それによると、競技会場の最寄りになる大江戸線国立競技場駅、ゆりかもめ台場駅、りんかい線国際展示場駅あたりは、競技開催日は通常の5~6倍の混雑になるということです。
もちろん、乗換駅として利用される「東京駅」「新宿駅」「永田町駅」の混雑も懸念されています。
さらに、都内の通勤ラッシュ時間帯はすでに最大限の輸送力とギリギリの過密ダイヤになっているため、鉄道会社が何か対策をとるのは難しいと言われています。
オリンピック期間中はリモートワークや時差通勤といった何らかの対策を始めている企業もあるようですが、対策検討は予定していないという企業も少なからずあるようです。
リコーはすでに、東京オリンピック開催期間中の2020年7月24日~8月9日は本社オフィスをクローズし、本社勤務の社員(約2000人)が一斉にリモートワークを行う事を発表しています。
ちなみに、2012年ロンドンオリンピックでは、政府の呼びかけでロンドン市内の企業の約8割がテレワークを実施。
これによって、交通網の混乱を回避することが出来たといいます。
日本もこのくらいできればいいですね…
東京都は一応、2020年のオリンピックに先駆け、スムーズビズを提唱しています。
スムーズビズとは?
スムーズな通勤や物流などの実現に取り組むことを目的とし、以下の3つを合わせた取り組みを指します。
・テレワーク
https://tokyo-telework.jp/
・時差Biz
https://jisa-biz.metro.tokyo.lg.jp/
・2020TDM推進プロジェクト
https://2020tdm.tokyo/
企業向けの説明会、導入支援やコンサルティング等、テレワーク導入の際に必要な費用の助成等も行っているようですので、対応を検討されている企業は一度見てみると良いかもしれません。
オリンピック開催のデメリットは?
東京オリンピック開催に伴って、さまざまな経済効果や雇用の増加など、いろいろなメリットが生じますが、それと同時にデメリットも予想されています。
今回は、デメリットについてご紹介します。
治安の悪化
オリンピックは世界最大規模のスポーツの祭典です。世界的な注目度も高いため、政治的な主張をするための活動やテロのリスクが高まることもあるかもしれません。
感染症リスクの増大
世界中から人が集まることで考えられる危険の一つに感染症があります。2020年現在も、新型コロナウイルスのニュースが大きく取り上げられていますが、オリンピックで東京に海外から人が集まることで、これまで予想もしなかった感染症の流行がおきる可能性もあります。
オリンピック不況
オリンピックを開催した国がその後、不況に陥るという話がよく聞かれます。
特に、莫大な開催費を投入するように変貌してきたオリンピックでは、開催した自治体が赤字を抱えてしまうケースも見られます。
その赤字は税金として回収しなければいけなくなるので、苦しくなるわけです。個人レベルでいうと、オリンピックへ向けて消費意識も高まりますが、オリンピック終了後はしばらく財布のひもも固くなる。
オリンピックで生じた雇用がその後どれだけ維持されるのかもわからないため、不安な気持ちが経済に悪影響を与えるということも考えられます。
最後に
ここまで、2020年の東京オリンピックが与える影響について書いてきましたがいかがだったでしょうか。
あと数ヶ月後には開幕する東京オリンピックですが、少なからず不安を感じた方もいらっしゃるのではないかと思います。
国や自治体、公共交通機関の方針や対策にも注目しながら、ぜひ私たちも対策を考えてみましょう。
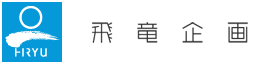

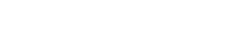
最近のコメント